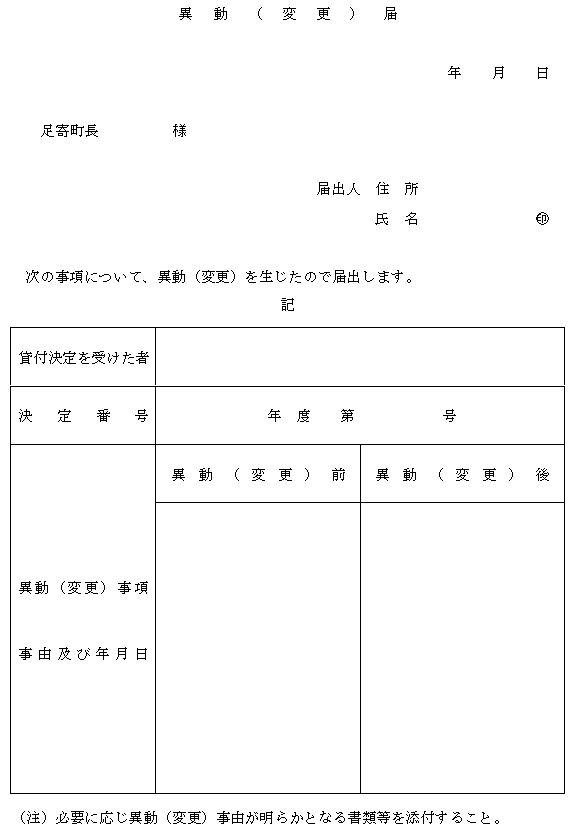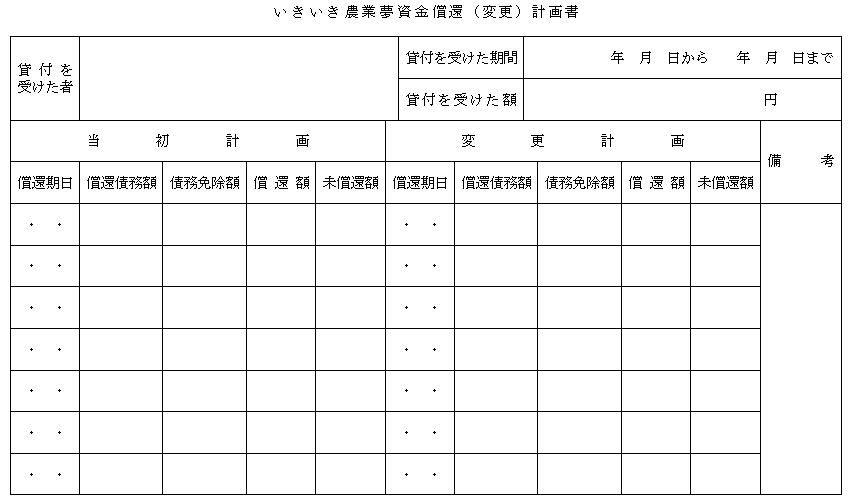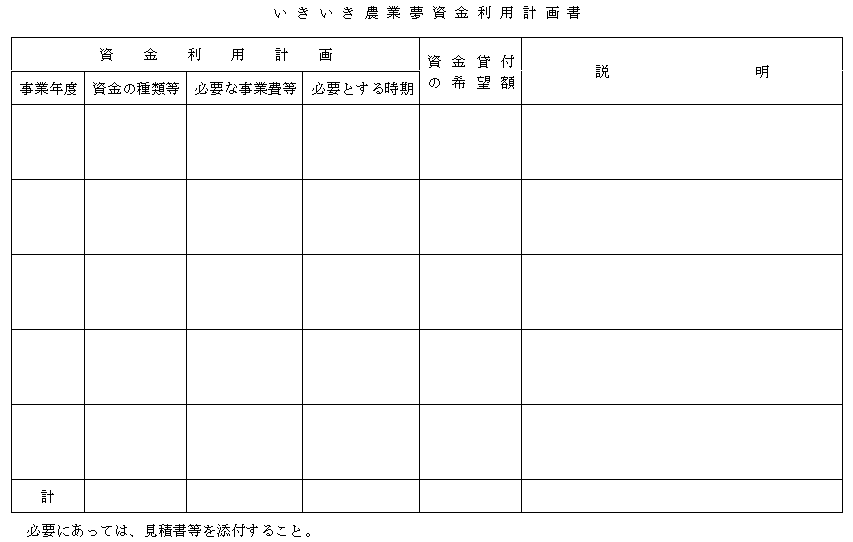○足寄町農業後継者就農育成資金貸付条例施行規則
平成10年9月18日規則第33号
足寄町農業後継者就農育成資金貸付条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、足寄町農業後継者就農育成資金貸付条例(平成10年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第1条に規定する親又はこれに代わるべき者(以下「親等」という。)とは、当該後継者の3親等以内の者をいう。
(認定後継者の認定基準)
第3条 条例第3条に規定する認定後継者の認定基準は、次に掲げる要件の全てを満たしている者とする。
(1) 本町に住所を有する者
(2) 親等の農業経営を継承し、その後継者として自ら農業経営を行うことが確実に見込まれ、かつ申請時から5年以上継続して就農することが確実である者
(3) 親等の所属する農業協同組合の長(以下「所属農協組合長」という。)の承認を受けた者
(4) 申請時の年齢が20歳以上45歳未満である者
(5) 申請時において年間150日以上農業に従事することが確実に見込まれる者。ただし、当該資金の借入期間中における研修及び実習は、農業従事期間とみなす。
(6) 就農開始日から起算して8年以内に申請した者
(7) 他の職業に就き再就農する場合は、当該貸付金制度を利用していない者であること。
(就農開始日の基準)
第4条 前条第6号に規定する就農開始日の基準は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に就農した者については、毎年1月1日を就農開始日とする。
2 20歳未満で既に就農している者にあっては、満20歳となる年度の1月1日を就農開始日とみなす。
(認定後継者の認定申請)
第5条 条例第3条に規定する農業後継者認定申請書(以下「認定申請書」という。)は、別記第1号様式によるものとする。
2 前項の認定申請書の提出にあたっては、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 就農計画書
(2) 親等の農業経営を継承し、又は農業に従事することを証明するもの
(3) 所属農協組合長の副申書(承認通知書の写し)
(4) その他必要と認める書類
3 町長は、条例第3条の規定により認定の可否を決定したときは、別記第2号様式による農業後継者認定・不認定通知書により申請者に通知するものとする。
4 町長は、前項の認定の可否の決定及び支援措置等の適正化を図るため、足寄町農業委員会、農業協同組合及び有識者等の意見を聴くことが出来る。
(使途)
第6条 条例第4条に規定する営農技術及び経営能力等の向上を図るために必要な資金の使途は、別表1に掲げるものとする。
(貸付申請及び決定)
第7条 条例第7条第1項に規定する申請書は、別記第3号様式によるいきいき農業夢資金貸付申請書に資金利用計画書を添えて町長に提出するものとする。
2 町長は、条例第7条第2項の規定により資金の貸付を決定したときは、別記第4号様式によるいきいき農業夢資金貸付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(貸付方法)
第8条 資金の貸付は、前条第2項の貸付の決定を受けた者の請求により行うものとする。
2 資金の貸付額は、前条第1項の資金利用計画書に基づき、その年度に必要な額を毎年一括して貸付するものとする。
(就農計画書及び資金利用計画書の変更)
第9条 認定後継者が第5条第2項第1号に定める就農計画書及び第7条第1項に定める資金利用計画書を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(賃借契約)
第10条 条例第8条の規定による資金の賃借契約は、別記第5号様式によるいきいき農業夢資金貸借契約書により締結するものとする。
(資金貸付の取消し等)
第11条 町長は、条例第10条の規定により資金の貸付決定若しくは資金の貸付を取消したときは、別記第6号様式によるいきいき農業夢資金貸付取消決定通知書により、当該取消しを受ける者に通知するものとする。
(資金償還明細書の提出)
第12条 資金の貸付を受けたものが、次の各号の一に該当するときは、その事由が生じた日から1カ月以内に別記第7号様式によるいきいき農業夢資金償還明細書を町長に提出しなければならない。
(1) 資金の貸付期間が完了したとき。
(2) 資金の貸付を取り消されたとき。
(3) 第14条の資金債務の免除を受けるとき。
(償還方法)
第13条 条例第12条の規定に基づく資金の償還については、貸付期間中の資金借入額の総額を年度割額を、毎年11月30日までに償還しなければならない。ただし、その全額又は一部を繰上償還することができる。
(債務の免除手続)
第14条 条例第11条の規定により資金の債務免除を希望するものは、償還年に生ずる債務額について毎年度、別記第8号様式によるいきいき農業夢資金債務免除申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その結果を別記第9号様式によるいきいき農業夢資金債務免除決定通知書により申請者に通知するものとする。
(償還減免手続)
第15条 条例第13条の規定により資金の償還免除を希望するものは、別記第10号様式によるいきいき農業夢資金償還金減免申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その結果を別記第11号様式によるいきいき農業夢資金償還金減免決定通知書により申請者に通知するものとする。
(償還減免の基準)
第16条 条例第13条に規定する償還の減免は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 死亡した者 未償還金の全部
(2) 精神に著しい障害が生じ介護を要する者 未償還金の全部
(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表に掲げる1級又は2級の障害に該当する者 未償還金の全部
(4) 身体障害者福祉法施行規則別表に掲げる3級又は4級の障害に該当する者 未償還金の3分の2
(5) 災害その他の特別な事由により、返還することが困難であると町長が認める者 未償還金の全部又は3分の2
(延滞金の減免申請)
第17条 条例第14条の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、別記第12号様式によるいきいき農業夢資金違約金減免申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その結果を別記第13号様式によるいきいき農業夢資金違約金減免決定通知書により申請人に通知するものとする。
(届出)
第18条 資金の貸付を受けている者が、次の各号の一に該当するときは、別記第14号様式による異動(変更)届を速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 住所、氏名を変更したとき。
(2) 親等が農業経営を中止又は廃止したとき。
(3) 親等の経営を相続又は継承したとき。
(4) 親等の農業経営を継承し、又は農業に従事することを中止したとき。
(5) 資金利用計画を中止又は休止するとき。
(調査)
第19条 町長は、資金の借入者に対し就農状況及び資金使途の状況について調査し、又は必要な報告を求めることができるものとする。
(資金貸付簿の備付け)
第20条 町長は、資金の貸付状況及び償還状況を明らかにするため、いきいき農業夢資金貸付簿を備えるものとする。
(雑則)
第21条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成14年5月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成17年6月30日規則第27号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の足寄町農業後継者就農育成資金貸付条例施行規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表1(第6条関係)
いきいき農業夢資金の種類(使途)
資金の種類 | 資金の内容、使途 | 貸付限度額 | 債務免除額 | |
経営技術高度化資金 | 機器導入 | 技術習得に必要なパソコン及び関係機器、ソフトウェア・制御装置等の購入費等 | 200万円以内 | 100万円以内 |
資格等取得費 | 農業経営に必要な資格を取得するために必要な資金 | |||
国内研修 | 国内の農家又は農業者教育機関等に1週間以上滞在して受ける研修に必要な資金。ただし、町及び農業団体等の補助がある場合は対象外とする。 | |||
海外研修 | 海外の農業事情視察又は滞在して受ける研修に必要な資金。ただし、町及び農業団体等の補助がある場合は対象外とする。 | |||
農業技術等開発資金 | 新技術等調査費 | 栽培又は飼養管理等の新技術を導入又は確立するために行う試験研究、実験等に必要な機材又は資材等の購入費又は賃料 | ||
新事業等開始資金 | 新事業等調査費 | 新規作物の導入及び生産方式の改善等に先立って行う先進地視察、市場調査、栽培又は飼養管理技術等の習得、試作費等 | ||
開始資金 | 新規作物の導入及び生産方式の改善等により新たな農業部門の経営を開始するのに必要な資材費、機械、施設、初度的経営費及びこれと併せて行う加工又は販売施設等 | |||
規模拡大資金 | 就農後に規模拡大した農地取得費又は賃借料を支払うのに必要な経費 | |||
地域農業推進資金 | 生産組織育成・技術等導入資金 | 地域農業を維持、発展するために行う組織経営体、生産組合及び営農集団等の設立又は加入に必要な出資金負担金等若しくは地域農業に必要な技術導入資金等 | ||
異業種交流等体験資金 | 都市住民及び消費者等との交流若しくは加工所や量販店、外食産業等での就労体験等に必要な資金 | |||
その他資金 | 特認資金 | 生活環境改善、土壌改良、観光農業市場開拓、結婚資金等営農技術及び経営能力等の向上に必要な資金で、町長が特に必要と認めたもの | ||
別記第1号様式(第5条関係)
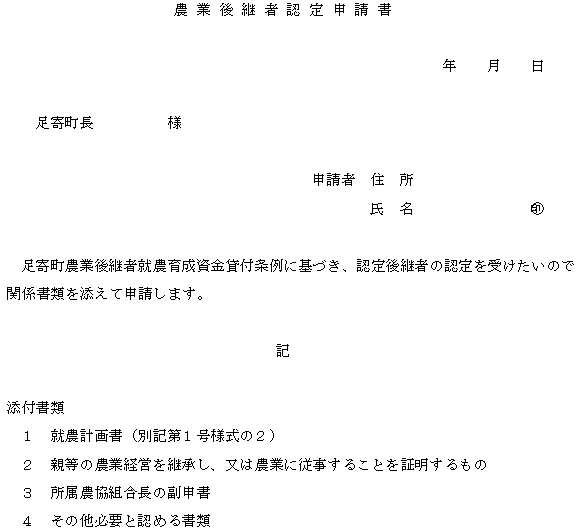
別記第1号様式の2(第5条関係)
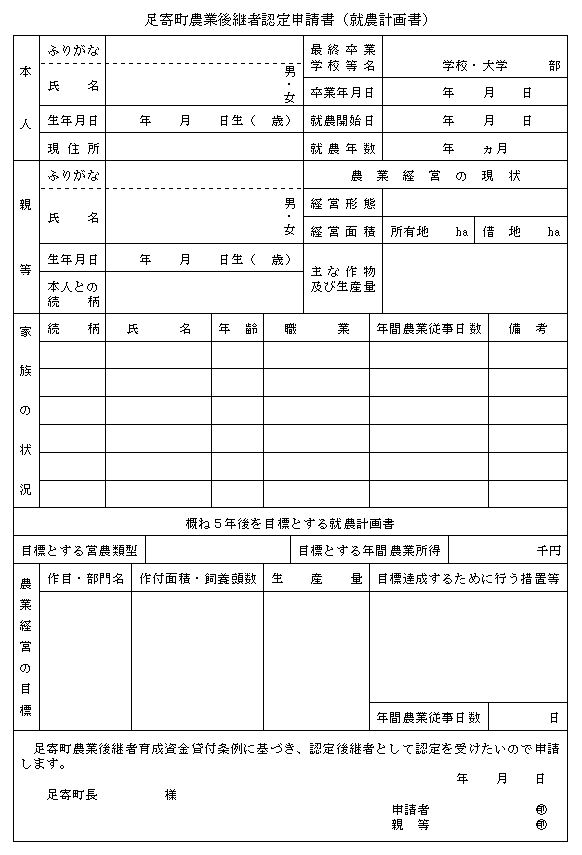
別記第2号様式(第5条関係)
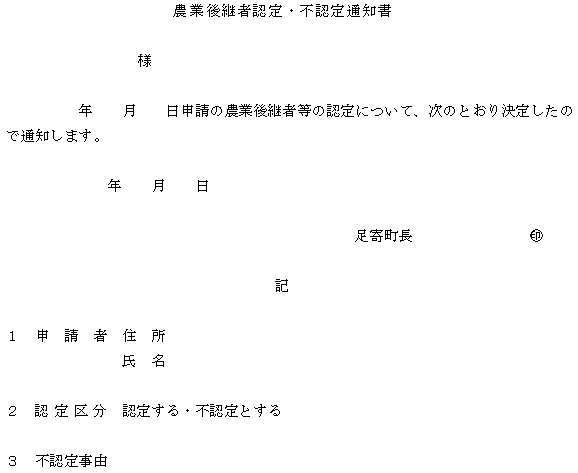
別記第3号様式(第7条関係)
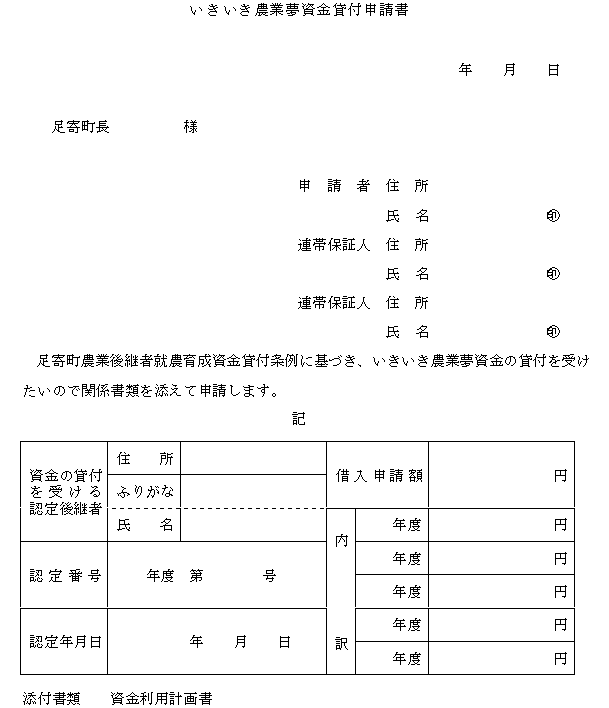
別記第4号様式(第7条関係)
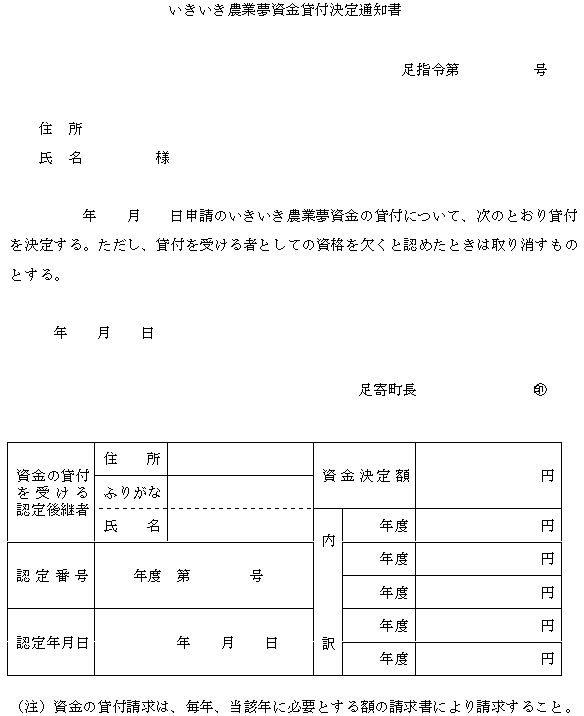
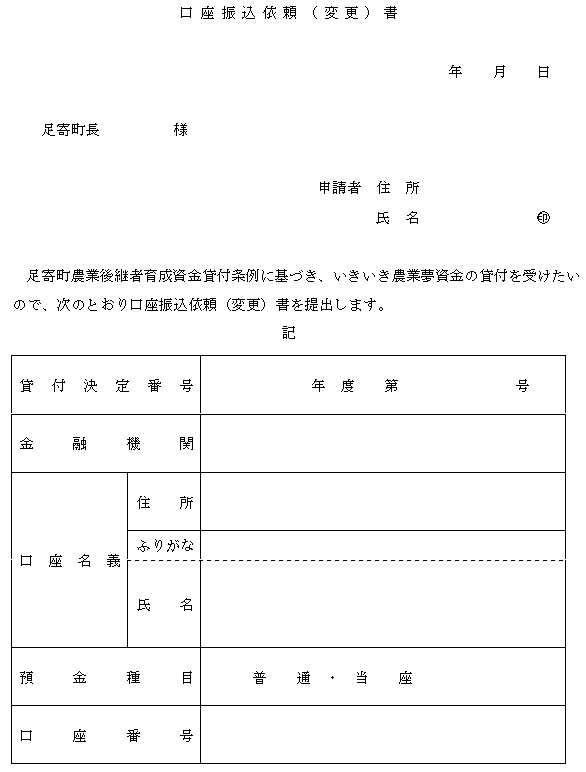
別記第5号様式(第10条関係)
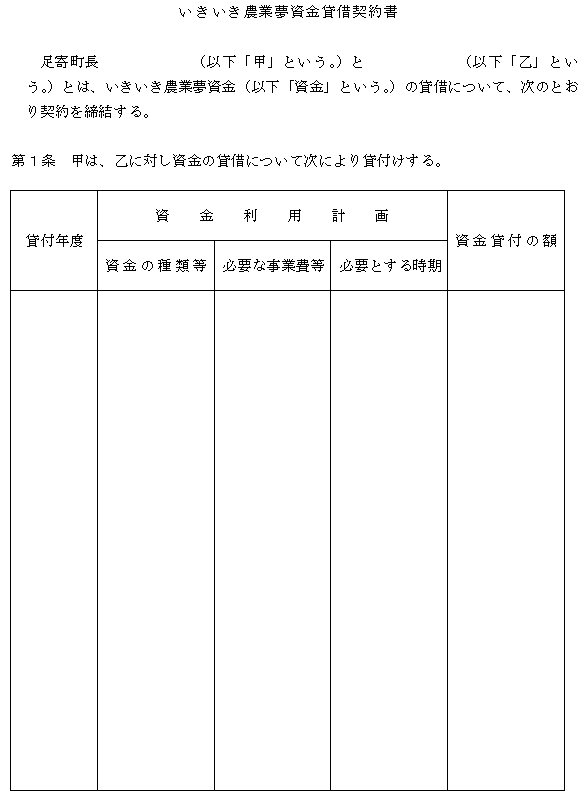
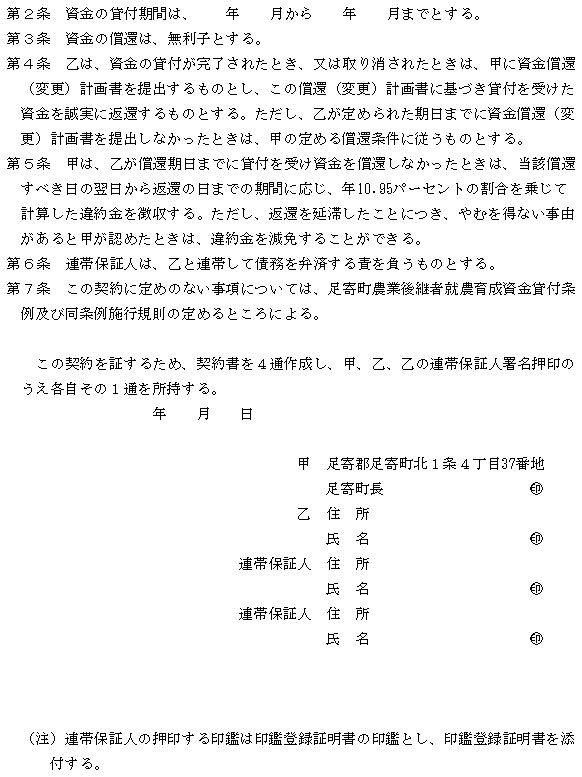
別記第6号様式(第11条関係)
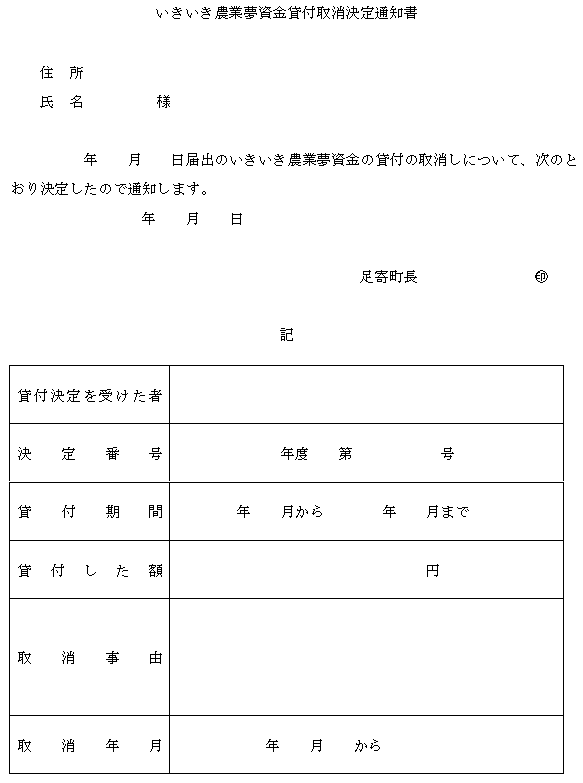
別記第7号様式(第12条関係)
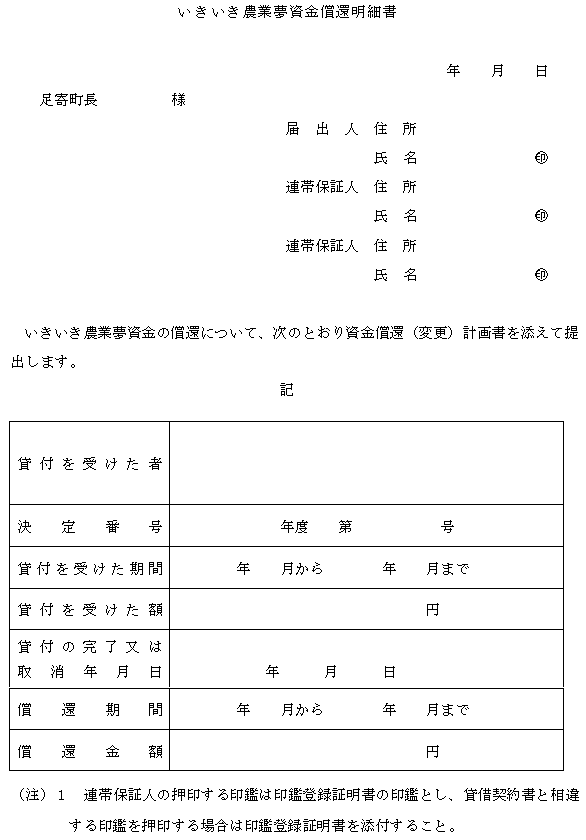
別記第8号様式(第14条関係)
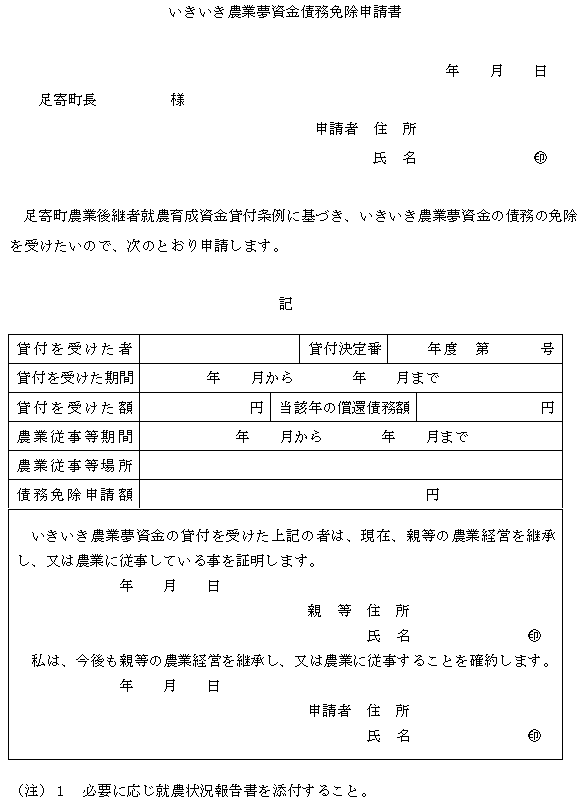
別記第9号様式(第14条関係)
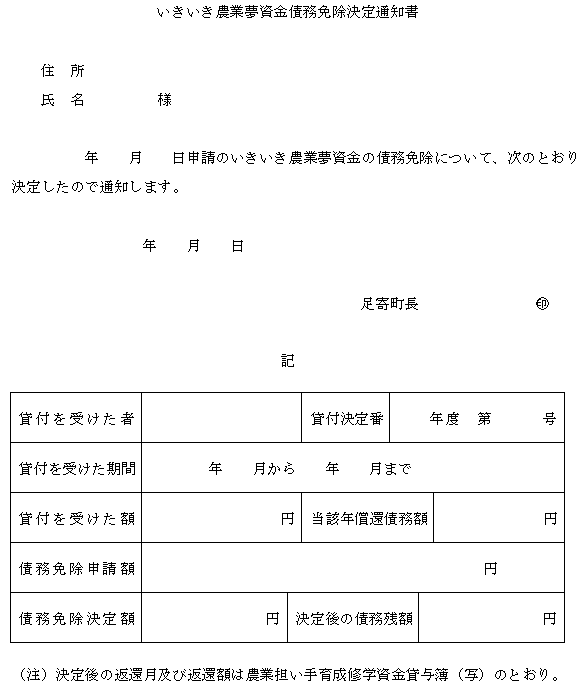
別記第10号様式(第15条関係)
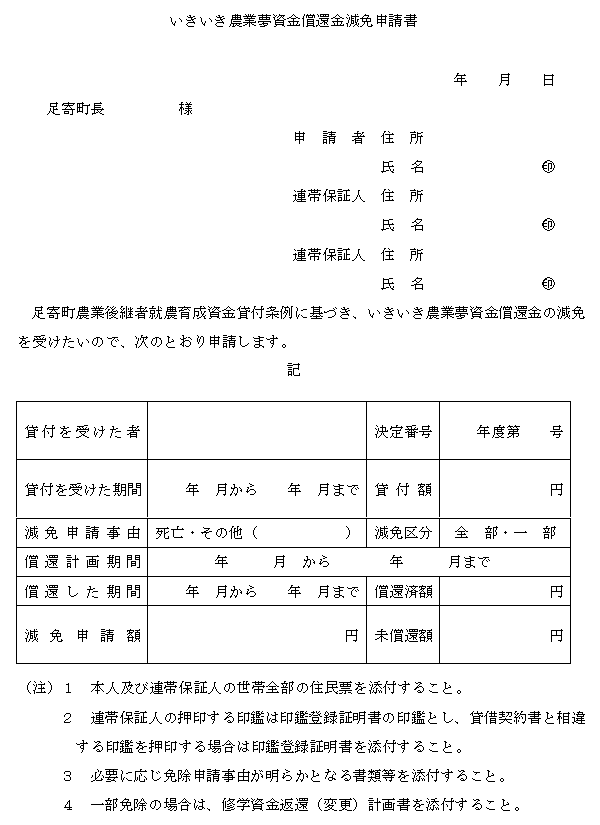
別記第11号様式(第15条関係)
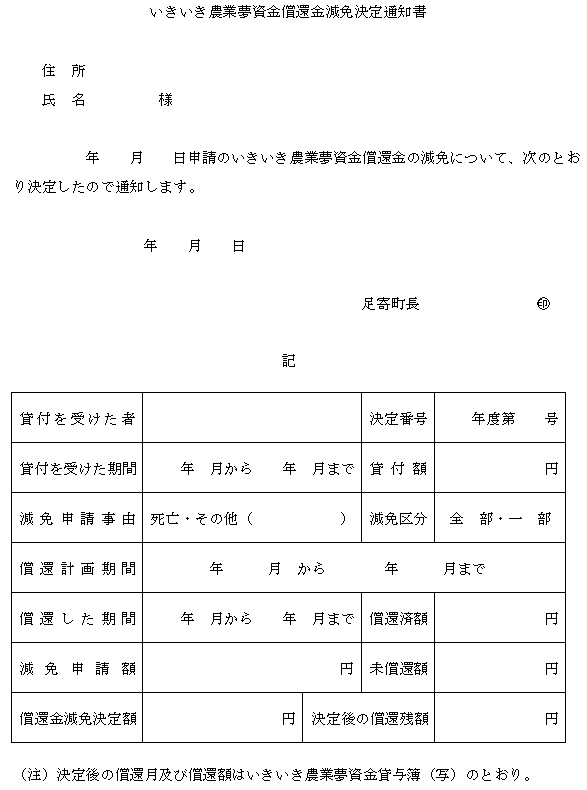
別記第12号様式(第17条関係)
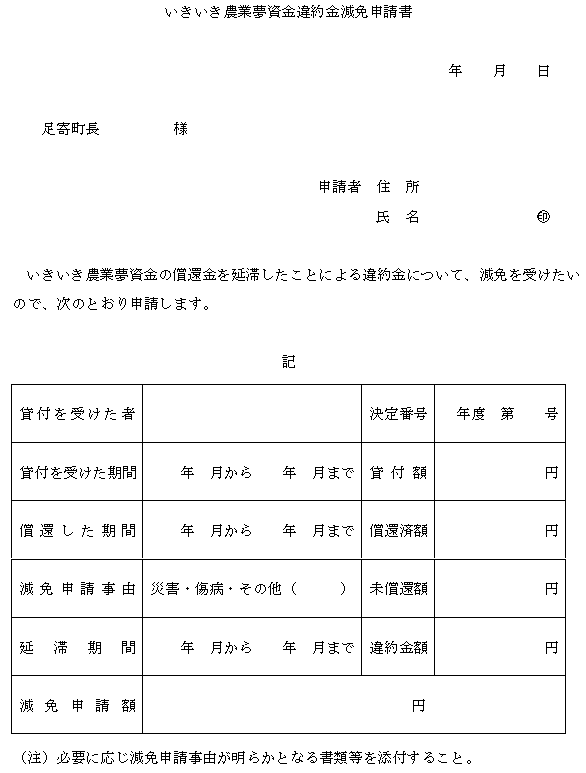
別記第13号様式(第17条関係)
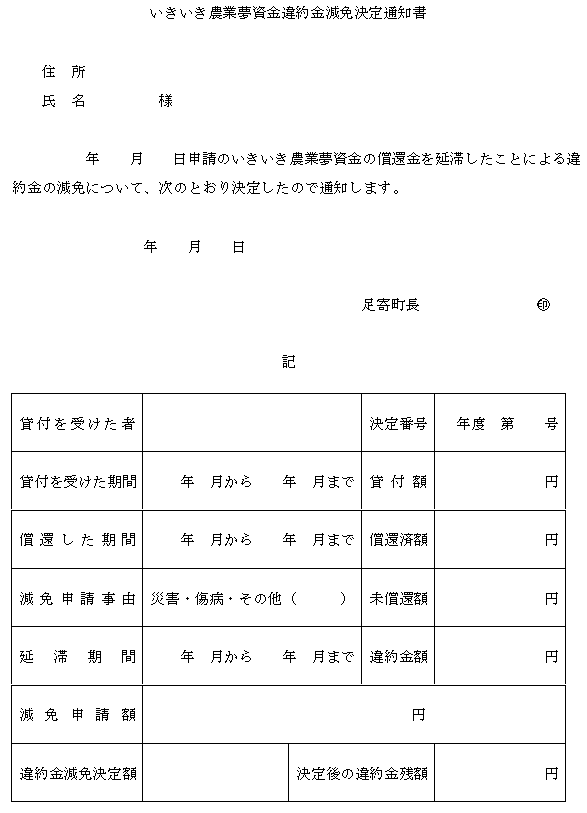
別記第14号様式(第18条関係)