足寄町の西部、芽登(めとう)地区の一角に、元足寄町立西中学校の校舎を利用した「木質ペレット」の製造工場がある。
「木質ペレット」とは、木材をオガ粉に砕き、木材の成分だけで圧縮成形した木質燃料の事だ。足寄の木質ペレットは、足寄で採れた「カラマツ」にこだわり、現在
2名の職員が、年間500トンの木質ペレットを出荷する。運営しているのは、「とかちペレット協同組合」。設立は2004年(平成16年)12月27日、足寄町内の10社と
町外4社の異業種の事業者が出資し、走り出した。そしてそこには、立ち上げメンバーの「町の今後を憂う心」と、「大人の遊び心」そして「情熱」があった。


「元々はね。1999年かな?九州大学とカラマツを使った産学共同研究が始まってね。それで僕も九大に出入りするようになってたんだよね。」そう話すのは、「とかちペレット協同組合」の現理事長であり、足寄の土建会社「外田組」の社長「菅原智美(すがわら ともよし)」だ。菅原さんの「外田組」は、当時、グループ会社の
「マルショウ技研」で煙突事業を展開していた事から、「木質ペレット」に着目していた九州大学から白羽の矢を立てられた。
ちなみに足寄でどうして九州大学なのかと言うと、実は九大は足寄町内に、3,713ヘクタール、東京ドーム実におよそ790個分の広大な演習林を持ち、それを管理したり、研究したりする職員が常駐している。当時の九州大学北海道演習林の林長は、「岡野哲郎(おかの てつお)」助教授。岡野先生と菅原さんは同じ年齢という事もあり、「馬が合ったんだよねぇ。」
菅原社長

岡野先生自宅

「岡野さんからね。『菅原さん、煙突屋なんだからペレットストーブ持ってこれないの?』って言われてさ。その当時、輸入住宅が流行ってて、北米や北欧から輸入している会社と付き合いがあったからね。誰か持ってこれるだろうって高をくくって『はい。いいよ!』って安請け合いしちゃったら、なかなか難しかったんだよねぇ。」
「まず、国内でペレットストーブ作っている会社はない。輸入ルートもない。最終的に並行輸入している所を見つけてやっとこさ2台輸入したのさ。で、1台は岡野さんの自宅。もう1台は助手の人の自宅に置いて燃焼実験の研究だよね。きちんと暖房として機能するのか?とか、灰はどれくらい出るのか?とかのデータを取る訳だよね。」
そんな風に手探りで木質ペレットの研究がスタートしたが、元々、ストーブが国内にないのだから、燃料である木質ペレットがあるはずもない。
「だからこれも輸入するんだけど、ペレットみたいに安くて重い物って割りに合わないのよ。だから、燃料としてではなくて、牛の敷料として輸入しているところから購入したり、輸入住宅の資材のクッション材という体で入れたり、あの手この手で手に入れてたねぇ。」菅原さんは、当時の苦労を思い出して笑い話のように話してくれた。「だから、ペレットの事は知ってたんだよね。そしたら町が『新エネルギービジョン』を策定するっていうので、岡野さんも僕も策定委員を頼まれた訳さ。」
そしてそこに集った男達こそ、その後「ペレットのある生活を文化に!」を合言葉に掲げ、木質ペレットを足寄の産業にすべく立ち上がった男達だった。


足寄町は、2001年(平成13年)に「新エネルギービジョンおよび木質バイオマス資源活用促進ビジョン」を策定した。「そしたらね。策定するだけじゃなくて、その先までやろうって言ってたのになかなかそれが進まなくてさ・・・。」
当時、新エネビジョンを担当していた役場OBの「岩原 榮(いわはら さかえ)」はその時の事をこう振り返る。
「いやぁ。菅原さんと、中島さん、家常さん、それから岡野先生が、代わる代わる役場に来て、オレを責める訳。『策定だけじゃないって言ってたべ!』ってね。笑」「でね。みんな役場で、大きな声で大きな夢を語る訳よ。笑」 そういう岩原さんも声は大きい。
「だからね。その翌年に岡野さんや、中島さん、家常さん、あと岩原さんとかで集まってさ。『このままじゃ林業ダメだよねぇ。』『木質ダメだよねぇ。』『足寄がダメになっちゃうよね。』っていう事で月に1回くらいのペースで集まりだした訳。まあ飲み会なんだけどね笑」菅原さんは悪戯顔でそう言った。そしてそれが、有志グループ「あしょろ森林工房」の始まりだった。
初期メンバーは、次の通り。「中島さん」とは、造林会社「宮口産業」の代表で、後に「とかちペレット協同組合」の理事長として、足寄のペレット事業を引っ張った「中島正博(なかじま まさひろ)」さん。頭脳明晰・理論派だったそうだ。そして「家常さん」は、同じく造林会社「イエツネ林業」の代表「家常雅弘(いえつね まさひろ)」さん。家常さんは、中島さんとは対照的に「理論」よりも「情熱」の人だった。涙もろく、ケンカっ早いところもチャーミングな方だったという。
そして、「岩原さん」。大きく、通る声がトレードマークのエネルギッシュな方である。その他、当時の北海道新聞社の本別支局長、十勝毎日新聞社の足寄駐在記者、
九大職員、足寄動物化石博物館館長などが参加していた。そんな個性的で異業種なメンバーが、菅原邸のガレージに集っては、酒を酌み交わしながら侃々諤々。
菅原さん曰く「目指す方向は一緒なのに、言い方が違うからケンカになるのさ笑」
「あしょろ森林工房」例会 左が中島さん、右が家常さん


「最初はペレットにこだわっていた訳じゃなかったんだよね。炭でもいいし、中島さんは、元々農業畑の人だったから、当時牛の敷料に『カールチップ』っていうのがあって、それを十勝でも作ってるところがあるから、それはどうか?とかね。」「で、そうこうしている時に、道の駅でエネルギー関連の展示会をやるっていうんで、『じゃあ展示してみよう。』って事になったり、その頃、滝上町で木質ペレットの生産が始まったりして、視察に行ったりね。で、じゃあ我々もペレットに特化してみようって話しがまとまった訳さ。」「で、まずはペレットを作ってみよう!って事になったんだよね。」
「あしょろ森林工房」は、まずは小さなペレット製造機を購入しようと、動き出し、補助金を申請するために有志グループではなく、正式な団体を作った。
それが今も続く、「足寄町木質ペレット研究会」通称「ペレ研」だった。初代会長には、中島さんが就任した。2003年(平成15年)の事だ。
「ペレ研」は、昔の足寄町公民館の調理実習室を研究室にし、夜な夜な集まっては、ペレットのテスト製造に勤しんだ。「カラマツはもちろんだったけど、色んな樹種や素材で作ったんだよ。例えば九大の先生が屋久杉を持ち込んで来たりね。あと岩原さんが、『どうしても堆肥で作ってみたい!』とか言い出してさ。みんなから反対されたから、一人で作ってねぇ。」「堆肥ペレットは燃料としては、NGだったけど、肥料として撒くとゆっくり浸透していくとか、撒きにくい場所でも撒きやすいとか、一定の効果は得られたんだよね。」
大の大人が、あーでもない、こーでもないと言いながら、目を輝かしていた事は想像に難くないが、彼らが当時作った色々なペレットは今も芽登の工場の事務室に大切に保管されている。
右から、中島さん、家常さん、八重樫さん、左端が岡野さん



ペレ研創成期を支えた人物の一人に「込山善兵衛(こみやま ぜんべえ)」さんがいる。
町内で「込山電器」というお店をやっていた。実はペレ研で、ペレット製造機を購入した際、オガ粉を少しづつ供給する装置も同時に必要で、それを購入すると、100万も150万もする事がわかった。すると、そこに登場したのが、善兵衛さんだ。「オレ、作ってやる!」と一言いい残すと、本当にその装置を作ってみせたのだ。それからというもの、善兵衛さんは次々に色々なものを作ってくれた。
「輸入のバーナーでペレットを燃やして喜んでたらさ。ドラム缶にそのバーナー付けて暖房機にしてくれて、その上、更に扉つけてオーブンにまでしてくれたりさ。」「ついにはバーナーまで自分で作ってたよね。」「皆でそのバーナーの事は、『コミヤマックス』って呼んでたんですけど笑」しかし、善兵衛さんの仕事はこれに留まらなかった。なんと、普通の反射式の灯油ストーブを改造してペレットストーブを作ってしまったのだ。
「あれ表に出したいなぁ。とっても捨てられなくてねぇ。」菅原さんは、笑っているような泣き出してしまいそうな、そんな顔をしてそう言った。
善兵衛さんはペレ研に多くのものを残して、2020年3月6日、天に召された。
込山善兵衛さん

込山さん自作のペレットストーブ


様々なメンバーがそれぞれの得意分野と「なんか面白そう!」という好奇心を寄せ集めて「ペレ研」の活動は、どんどんとその幅を広げていく。まだまだ認知されていない木質ペレットの「普及啓発活動」。ペレット自体の質を上げる「木質ペレット製造技術開発」。そして最終的な目標となった「木質ペレット製造事業の立ち上げ準備」。2003年には、木質ペレット先進地のスウェーデンへ視察にも出かけた。そして男達の夢は、「木質ペレット製造の事業化」1本に絞られていく。
あの日語った大きな夢の形が見えてきた。
役場OBの岩原さんは言う。「こないだね、役場の林業担当の職員にさ『岩原さん、昔のペレットの資料見ました。よくあれだけの事やりましたねぇ。』って言われたんだけどね。いや、あれは役場の業務の中だけの資料なんだよってね。その他にプライベートでどれだけやってたか。」「本当に自分だけじゃなくてね。中島さんだって、家常さんだって、菅原さんだってさ。自分の本業やりながらだからねぇ。集まるべって言っても普通誰か彼か来れないしょ?全員来るんだよ毎回。いやぁすごかったよ。みんな。」興奮気味に話す岩原さんの声がまた一段大きくなった。
スウェーデン視察



木質ペレット生産の事業化に向け、「ペレ研」の情熱は少しづつ周囲に伝播していった。大きかったのは、2006年に完成の足寄町役場の新庁舎にペレットボイラーが導入される事が決まった事。
しかし事業化へ大きく前進はしたが、難題は山積みだった。製造工場をどうするか?運営はどうするか?販路は?そして実際に現場でペレットを製造する人材はどうするのか?ペレ研メンバーはこれを一つ一つクリアしていく為に日夜奔走した。
製造工場は、廃校となっていた中学校の校舎に的を絞るが、廃校になっているとはいえ、本来の使用目的でないものには大きな障壁があった。これを担当したのが、
役場職員の岩原さん。「当時、『地域再生計画』っていうのを自分がせっせっと作ったんですよ。ところが平成大合併の時代で足寄も合併の話しが進みかけていて、これを基に計画を立てていたところ、その話しが頓挫して、また一から計画を立て直したんだよねぇ。そうやってようやく当時の小泉首相から旧西中の用途外使用の許可が下りてねぇ。これは僕一人でやったので、その苦労は周りはわからないんだよね笑」そう話し、ポツリと「これは書かなくていいからね。」こう呟いた。
『書くな』というのは、『書け』という振りと判断し、書いてみた。
そんな岩原さんのご苦労もあり、芽登の旧西中学校の校舎を再利用する事が出来たお陰で、随分とイニシャルコストを下げる事が出来た。
並行して運営をどうするのか? メンバーの家常さんは、「地域の資源を地域で地域のために生かすなら、足寄だけでは完結しない。それなら『十勝』をターゲットに、異業種で、十勝に仲間を増やして運営するべきだ。」と強くこだわった。
メンバーは足寄町内の事業者を中心に、十勝の林業関係・建築土木・設備・機械製造・運送・そして燃料販売などの事業者を粘り強く説得し、遂に2004年12月「とかちペレット協同組合」を設立。理事長には、中島さんが就任した。
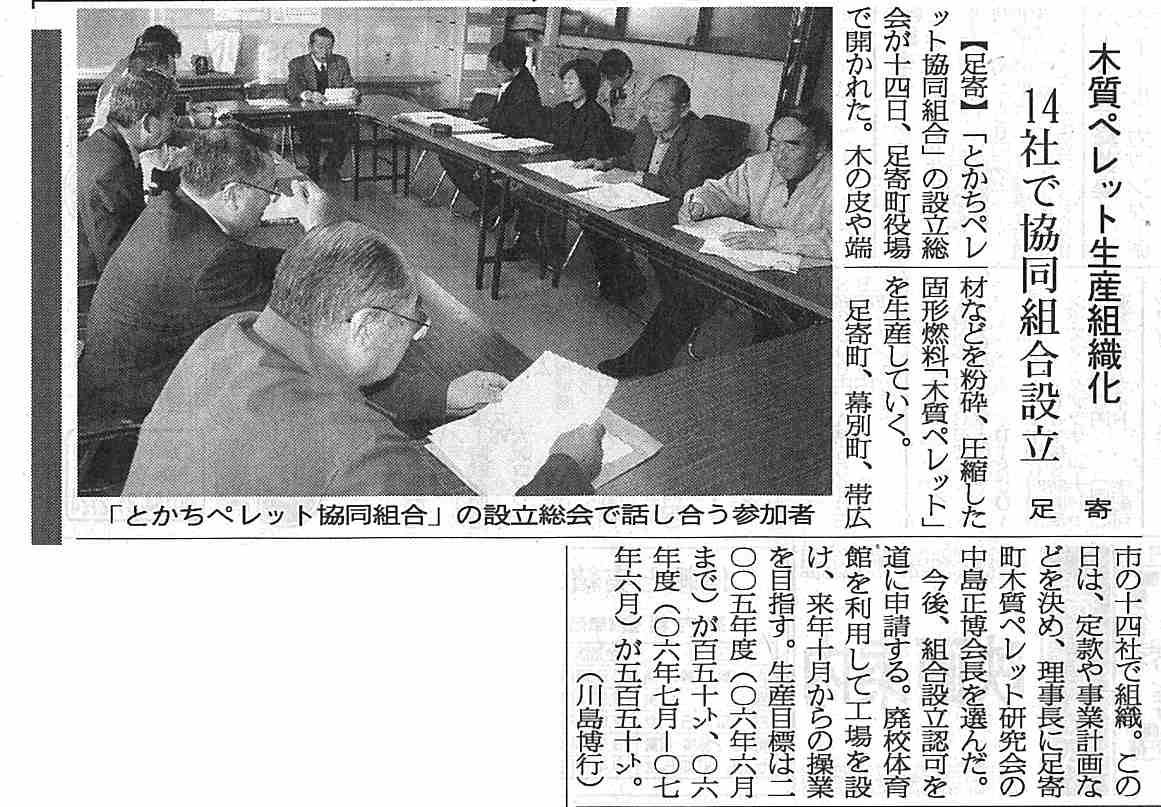

2004年の暮れに立ち上がった「とかちペレット協同組合」だったが、大きな問題が一つ。「一体誰が実際に工場で製造・運営をするのか?」翌年稼働するというのに
その人材は見つかっていなかった。ペレ研メンバーが事業化に向け、走り回る一方で、その動きを客観的に見ていた男がいた。
足寄で割りばし製造業を営んでいた「タイセツ」の代表「八重樫 明(やえがし あきら)」だ。八重樫さんが、ペレ研メンバーと関わるようになったきっかけは、家常さんだった。「割りばし作っているとチップが出るもんだから、それを大手の製紙会社に収めてたんだよね。で、年に何回か帯広で会合があるんだけど、足寄では会わないのに、そこに行くと会う足寄の人がいたんだよね。それが家常さんさ。」「それで、家常さんからこんな会があるから来ないかい?って『森林工房』に誘われて行くようになったんだよね。」いかにも温厚そうな八重樫さんは、穏やかな口調でそう話してくれた。
そんな八重樫さんだから、メンバーの発言や動きを客観的に見ていた。「なんだか、組合作って本格的にやろう!って言ってるんだけど、あんまりそんな感じがしなかった。家常さんに『それで一体誰がやるの?』って聞いても『いや知りません』って言うしね笑」
見かねた八重樫さんは、「もし誰もやらないなら、オレがやってもいい。」と手を挙げた。「もう渡りに船だよね笑」八重樫さんは、そういって微笑んだ。
しかし、どうしてわざわざ苦労の道を選んだのであろう?
「平成に入って、割りばし業界も中国からの輸入品が大量に入って来て斜陽の時代だったのもあるんだよね。」
滝上町出身の八重樫さんは、離農後、割りばし工場の工場長を務めていた父が独立し、足寄の旭町に工場を出すに当たり、弟さんらと共に足寄にやって来て、家族で割りばし工場を営んでいた。「『利久箸』ってのを作っててね。日に14万膳くらい作ってたねぇ。いい時だと従業員も32人。その他に内職の人も70人くらいいたから。」
ペレット工場でも一緒に働いた奥様の「直子(なおこ)」さんも、滝上出身で、八重樫さんの父が務めていた工場の専務が間を取り持ち、1975年(昭和50年)に結婚した。割りばしの製造に関しては、「特許も2つくらい取ったんだよ。」と順風満帆だった。しかし、前述の通り、時代は八重樫さんの工場も飲み込んでいく。
「最後は二人で細々とやってた感じだったねぇ。」
そんな風に割りばしに見切りをつけ、ペレット工場の製造に手を挙げた八重樫さんだったが、現場は現場の苦労が満載だった。「工場作って、今年の秋には稼働させるべって言っているのに、1月になっても2月になっても図面すら出来てないんだもん笑」「とりあえず、申請するのに僕がえんぴつ舐め舐め書いた図面出してねぇ。」
そんな裏話もありつつ、「とかちペレット協同組合」のペレット製造工場は、2005年10月に完成。いよいよ本格的なペレット製造へ歩みを進める。
公募していた製品の名前は、「エコット」に決まった。



八重樫さん

体育館から工場への改築写真(八重樫さん所蔵)


「工場が稼働しても不具合が多くてね。」「割りばしやってたから、製造業は慣れてると思ってたんだけどまあイイものが出来なくて、出来なくて・・・。」
ペレットを作る際、材料の水分量が多いと乾燥ムラが出来るため「そこがカギだ。」と八重樫さんはいう。
「今思えば笑い話だけど、採って来たばかりの材料ですぐ作ってね。水分量が多くてイイものが出来ない。」「2週間悩んだね笑」 横にいた奥様が、「毎朝7時半に出かけて、終わるのが夜の9時、10時だったもんね。」。そう話してくれた。
「家常さんや岩原さんなんかが工場に来ては、『まだ出来ないか?まだ出来ないか?』ってね笑」「その内に夢にまで見るようになってねぇ笑 それくらい苦しんだね。実は。」八重樫さんは、教えを請おうと同業者に連絡する。「だけど、なかなか教えてくれないんだよ。何言うかと思ったら『原料に勝る技術なし』ってね。」
そんな禅問答のようなやり取りを経て、「『原料に勝る技術なし』今は、確かにそうだと思う。」と話してくれた。
八重樫さんご夫妻、奥様は2024年いっぱいで工場を辞め、八重樫さんご自身も、2025年6月30日を持って現場を離れた。奥様の直子さんは、この20年を「まあ割りばしも、もううまくいってなかったし、お父さんも新しい違うことやってみたいってのもあったと思うのね。だからね・・・良かったと思う。」と、そんな風に振り返った。苦労して、工夫して、そして助け合ってペレットを作り続けた20年だった。
八重樫さん製作の工場レプリカ


八重樫さんご夫妻

足寄の木質ペレットの動きにいち早く着目した男が帯広にいる。
創業75年、十勝っ子ならお馴染みのパン屋「株式会社満寿屋商店」代表取締役社長「杉山 雅則(すぎやま まさのり)」氏。
2000年前後、満寿屋では、「地産地消」を実現すべく、パンの原料はもちろん、燃料も地元のものを使えないか?と模索していた。
「当時、石窯を開発しようって話しが進んでいて、燃料も地元のものをと探してたんですよね。」「そしたら足寄で木質ペレットなる燃料をやりだすらしいという話しを聞いて、すぐに足寄に行きました。」足寄町役場の駐車場で開催された展示会を訪れた杉山社長は、木質ペレットに可能性を見出したが、「日本にはまだペレットオーブンがなかったんですよ。じゃあ作ろうって事になり、移動式のペレット窯にしようと決まりました。」「ただ、足寄の人もペレット石窯を作った事がなかったので、当時京都に有名な石窯パン研究家の『竹下晃朗(たけした あきろう)』先生っていう方がいて、先生に相談の連絡をしてみたら、なんと既にペレット石窯を作った経験があったんです。それで、竹下先生にアドバイスをいただいて、更に簡単な図面も書いてくれたり、窯に使うレンガの手配までしてくれたんです。
それを元に込山さんが石窯を作ってくれたのが、うちの第1号のペレット石窯なんです。」
満寿屋のペレット石窯1号機は、2005年6月19日の帯広市「八千代牧場まつり」でデビューを飾り、その後も、十勝管内のイベントや満寿屋のイベント、更に食育活動で大活躍。ペレット石窯を使用した出張ピザ作り教室は、この20年でおよそ900回を数え、延べ参加人数は約4万人。近年の満寿屋の新入社員の中には、子どもの頃にこのピザ教室を体験した社員もいるそうだ。
2005年八千代牧場まつり

2025年八千代牧場まつり

2025年八千代牧場まつり

2025年八千代牧場まつり

その後、翌2006年に芽室町の「めむろ窯」に2号機。2008年に杉山社長が十勝の仲間と立ち上げたレストラン「ビストロ・マリアージュ」に3号機。
「ビストロ・マリアージュ」は既に閉店しているが、その後、学生時代にマリアージュで修行をしていた「小久保 康生(こくぼ こうせい)」シェフの「マリヨンヌ」に引き継がれ、今現在は、まだ稼働していないものの、小久保シェフ曰く「お店は全面改装したのですが、こちらの窯は是非残してこれから使いたいと考えてます。」との事。そして4号機は、帯広市稲田町にある「麦音」にパン用の窯として設置。5号機は、2010年に現在は閉店している帯広競馬場内にあった「ピザ・ラ・バンバ」に置かれ、2011年に「麦音」の4号機と入れ替えられた。そして6号機は、芽室町の「めむろ窯」が、2014年にリニューアルした際に、2号機と入れ替えられ、現在までに都合6台のペレット石窯が作られている。
杉山社長に話しを伺うと、ペレット窯でパンを焼くのはなかなか簡単ではないようで、「ピザに向いているし、イベントや食育活動にもパンよりもピザの方が、簡単なので、今はピザを焼くのにペレット窯を利用していますね。」「『地産地消』にこだわりたかったが、エネルギーも地場のものを使えて良かった。」「足寄の皆さんにも
お世話になりました。特に込山さんには、今『麦音』にある水車まで造ってもらってまだ全然問題なく動いています笑」そう話してくれた。
杉山社長がまだ出来てもいなかった足寄のペレットに着目し、伴走してくれた事は、組合設立の際に家常さんがこだわった「十勝に落とし込む」という考え方の元に
なった出来事だったのかもしれない。


「めむろ窯」ペレット石窯

込山さん製作「麦音」の水車

満寿屋商店 杉山社長

あの日役場で「大きな声で大きな夢を語っていた」男達がいなければ。彼らが「足寄の森林の活用」について。「足寄の自然エネルギー」について。「足寄のまちおこし」について語り合わなければ、足寄のペレットの火が灯る事はなかった。
「家常雅弘」さんは、2005年ペレット工場のこけら落としを終え、1ヵ月も経たない11月28日不慮の事故で。
「あしょろ森林工房」「足寄町木質ペレット研究会」そして「とかちペレット協同組合」と常にリーダーとして夢を支えた「中島正博」さんは、2021年3月6日、闘病の末。共に帰らぬ人となった。
プロジェクトの精神的支柱だった「岡野哲郎」さんは、2004年に九州大学から信州大学に移り、農学部・農学生命科学科・森林・環境共生学コース教授として現在も森林研究を続け、九大時代から取り組む研究の為、ほぼ毎年足寄を訪れている。
「菅原智美」さんは、中島さん亡き後「とかちペレット協同組合」理事長として、事業を取り仕切り、「岩原 榮」さんは、民間会社のオブザーバーとして活動する中、「足寄町ペレット研究会」の事務局として今も活動を支える。
いつもグループを先頭でけん引してきた中島さんがある取材でこう話している。
「木質ペレットは目的ではありません。手段です。」あくまでも目的は、「地域振興」。そのための「手段」の一つがたまたま木質ペレットであったという。
しかし、その「手段」の中には、彼らやこれまで関わった産学官の人々の「夢」や「想い」や「哲学」がギュッと詰まっているのだ。
男達が灯した足寄のペレットの火を決して消すことは出来ない。

「足寄の木質ペレット」
とかちペレット協同組合 https://www.facebook.com/tokachipellet/?locale=ja_JP
満寿屋商店 https://www.masuyapan.com/
Special thanks to 杉山雅則氏 (株式会社満寿屋商店)
小久保康生氏(マリヨンヌ)
キーン竹下桃子氏
写真提供 菅原智美氏(株式会社外田組・株式会社ラポラ)
八重樫明氏(株式会社タイセツ)
菅原耕氏 (株式会社ラポラ)
※ コラム内の情報は、2025年7月現在の情報です。
